先日の記事では、健康被害を受けないために真鍮を削るための下地準備をしました。
今回は、実際に真鍮を削って使えるところまで完成させます。
材料
- 真鍮のブロック(お好みのサイズで)
- 真鍮の丸棒(これもお好みと、自分の持っている道具との兼ね合いで決める)
焼印になるブロックの作り方
キモとなる真鍮のブロックを、ルーターで削って行く作業です。
デザインを決める
まずは作りたい焼印のイメージを決めます。
今回は依頼だったので、メールでロゴの文字が送られてきました。
色々なサイズにして実際に並べて見ることで、どれがしっくりとくるのかを決めて行きます。
紙がもったいないので、とにかくたくさんのパターンを一枚の紙に印刷します。

しっくりとくるものがあれば、真鍮に合わせてカットし糊付け。
色々と試して見たが、スプレー糊が一番調子がいいようだ。
糊付けができたら、けがいてデザインに合わせた傷をつけて行きます。
ルーターで削っていると紙がどんどんなくなって行き、ふとした拍子にベリッと全部いってしまうこともあるので、けがいておけば一安心です。
カッターナイフや革細工で使う針状のものを使ったが、傷さえつけばなんでもいいと思います。
真鍮はとても柔らかいです。


けがきが終わったら、実際に削って行きます。
ルーターで削って行く
ルーター について
ここの作業が、焼印作りのキモになる部分で、一番楽しい部分なのは間違いないです。
ルーターはいいものを用意した方がいいと思います。
以前プロクソンのものを使っていたが、トルクが弱いのか全然ダメでした。
ドレメルはアタッチメントも豊富だし、アメリカにいたときもみんな使っていた信頼の置けるメーカーなのでおすすめです。
ちなみにアメリカ人はルーターのことをズバリ「ドレメル」と呼んでいました。
色々な種類があるが、僕はバッテリー式のmicroという名前のものを持っているのですが、なぜか当時の4倍の4万円くらいになっており全然お勧めできないです。
今買うならこれですね。
ルーターをあれこれ色々なところに持ち出したりはしないだろうし、ケーブル式の方が電池は気にしなくていいからこれでことは足りると思います
ビットについて
先端のビットに関しては、色々と使って見て調子よく削れるものを選ぶのが手っ取り早いです。
僕にはこの形状のものが一番合っていたし、よく使っていました。
すぐに折れるし、サイズは色々あるので、やはり実際に試して見るのが一番の近道だと思います。
幸い、ビットのセット販売もしているしルーターを買うと色々ついてくるので、全部使って見るといいと思います。
ちなみに東急ハンズでドレメルでないところのセット(10個セット1000円〜2000円くらいだった)を買ったところ、全然削れなかったので(日本製だったのに。。)ビットは値段相応だと思った方がいいと思います。
普通のものは一個400円〜はします。
削る
それでは実際に削って行きます。

コツとしては、
- 奥から手前に引きながら削って行くこと。
- 奥に滑っていこうとするので、奥に滑ってしまってもダメージが出ないように残したいところは進行方向に置かず、うまく動かしながら削る
- 削れてしまっても全体を紙やすりで整えてダメージをなかったことにできる
- 深さは2mmもあれば十分
- 油性マジックでマーキングしながら削る
というところでしょうか。
自分でやって見て覚えるしかないと思います。
集中力がそんなに続かないので数日かけて削るのが完了。

真鍮ブロックを切る
これは金属用のノコギリでゴリゴリとやれば切れる。時間がかかるけど、ルーターなどで切るよりもまっすぐに切れるし、粉がそんなに出ない。


ブロックと棒の結合
A. タッピングする
次に真鍮棒とブロックを接続する。真鍮の焼印の作り方を調べると、バーナーを使ったロウ付けを行なっている方を見るが、ロウ付けは素人には難しすぎる。。。記事の下の方に実際にやって見た記録もあるが、参考にして欲しい。めちゃくちゃひどいことになっている。
おすすめなのは、タッピングという技術を使う方法。これは、ブロックにネジ穴を作り、某の方はネジ山を作ることで、ネジネジと結合する方法だ。失敗するとすれば、ちゃんとドリルのサイズを確認していなかったくらい(経験済み)だし、火を使うわけではないので危険も少ない。
以下のブログに、ねじを切る方法が詳しく記載されているので参考にしてみて下さい。
ホームセンターに売っているタップダイスセットというものを買ってきた。

ブロックに穴を開ける
穴が貫通しないようにドリルにマスキングテープをして、深さをコントロールし垂直に穴を開ける。棒より少し小さい径で掘る。

ダイスで棒にネジ山をつける
ダイスを切っている途中の写真が抜けてしまったが、このようになる

ブロックの穴にネジ山をつける
ゴリゴリとネジ山をつけていきます

結合し、真鍮棒を好みの長さに切る
今回はグラインダーを使って切りました。ノコギリでもOK

B. ロウ付けで結合する場合
ロウ付けとは、溶接と半田付けのちょうど中間あたりに位置する結合の方法で異種の金属同士も繋げることが可能。
ロウ付けで結合する場合に必要になってくるものは以下の通り。
- ガストーチ(業務用のやつ)
- 銀ロウ
- フラックス
- コンクリートブロック
まず、コンクリートブロックにうまいこと真鍮を固定する。木工のクランプを使ったが、なかなか調子はよかった。
地面も思い切り炎で焼かれるので、ブロックを忘れずに敷いておく。


隙間にフレックスを流し込む。

最後に、バーナーで加熱して銀ロウを流し込んで行く。写真右下に写っているのが銀ロウだ。
バーナーをしながら撮影するのは無理だった。溶接と同じで、熱したところに銀ロウを当てて行くとすぐにふにゃふにゃと液状になる。これが固まって結合されるというわけだが、あまりに難しかったのでもうやりたくないしお勧めできない。

こんな感じでかなり不細工な形で繋がった。

ロウ付けで結合したい場合は、こちらのサイトを参考にするといいと思う。この人のブログ、結構好き。
とにかく完成!
メインのパーツが完成した。焼印をする際に角が当たってしまわないよう、角を落としてある。
あとは森に行って適当な太さの木の枝に、真鍮棒を突っ込もう。愛着がグッと湧いてくる。


では実際に焼きを入れて見る。
暑くなるまで火で炙る。

何度か捨てても良い木にテストして、丁度いい温度にする。
いよいよ焼きを入れる。

できた。

やって見ると、手間はあれどそんなに難しくはない。
そして達成感は素晴らしい。
以前電気につなげて火力をコントロールするタイプのものも作ったことがあるが、やはり本物の火でやった方が男前だしテンションも上がる。
一度作れば一生使えるので、一家に一つ。自作焼印はおすすめだ。

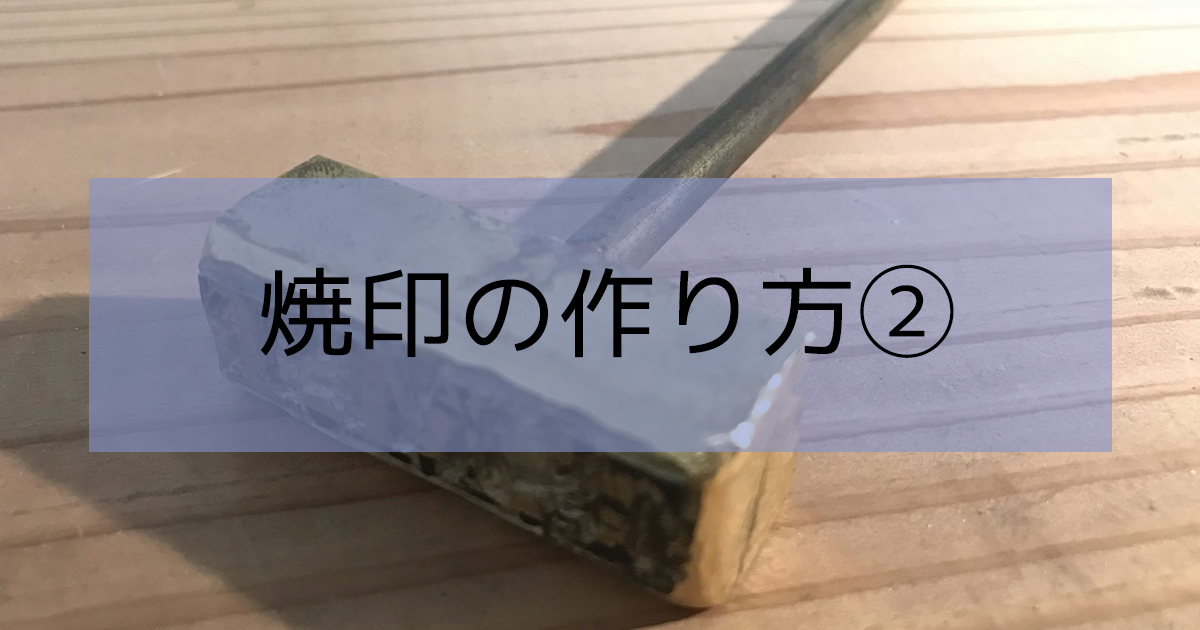



コメント